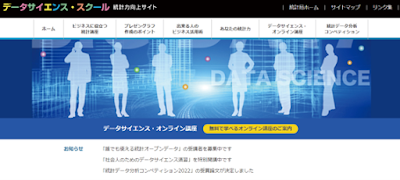ある学校の5教科のテスト。平均点は300点(国語・数学・英語は平均点が40点。理科・社会は90点)だったとする。
ちょっと良かったAさん320点(国70点、数80点、英70点、理50点、社50点)と
ちょっと悪かったBさん270点(国30点、数30点、英40点、理80点、社90点)がいたとする。
AさんとBさんは平均300点に対し50点差なので、すごく大きな差ではない。
ただ、国数英の主要3教科で比べると、平均120点に対し、Aさん220点、Bさん100点となり、ダブルスコア以上の差に。
理科と社会の暗記が得意なBさんは、Aさんと違って苦労しそうな雰囲気である。一方、Aさんは自力勝負であまり勉強しない点が、理社の悪さに。
突然、意味不明なことを書いたが、これが先日のCBnewsの記事の内容。評価軸が5教科から3教科に変わるなら、いままでと違う差があぶり出される。自分の病院がAさんタイプか、Bさんタイプか。どちらであるか把握しておくべき(もちろんテストの話などではなく、看護必要度のデータ分析結果を基に、対策やあるべき評価制度などについて真面目に書いた)。
B項目廃止なら同時に評価すべき取り組みとは - CBnewsマネジメント
(最近掲載してもらったと思ったけど、18日掲載なので、もう10日くらい過ぎてた。ここ最近の記憶がない・・・)
ちなみに、マニアックな話をすると、5教科のテストは、平均点も分散もばらばらで、それをただ単純に足しただけでは、総合力を判断することはできない。今回の例のように平均点が大きく異なっていれば、実力のある生徒は、国数英では差がつきやすく、理社では差がつきづらい。5教科を均等に足した評価をするならば、点数の分布を合わせる必要があり、一般的なのは偏差値だろう。5教科の平均偏差値(5教科の合計点の偏差値ではない)であれば多少ましになる。ただ、それも絶対ではなく、結局、科目ごとの点数の分布次第というのが難しいところだ。
なお、今回登場したAさんでもBさんでもない、とても成績の悪いCさんが同じ屋根の下に暮らしていて、大変悩ましい・・・ということを愚痴りたくて、ついついこんなブログに。